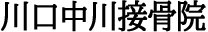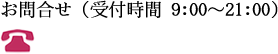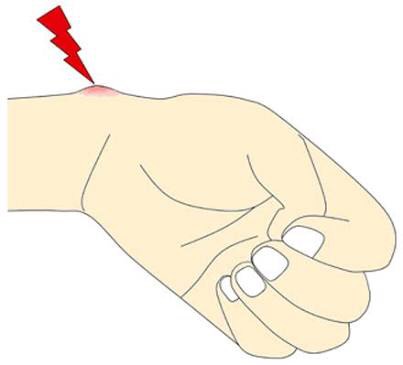院長ブログ
2019年06月18日
こんにちは。今回は肉離れについて
伝えていきたいと思います。
お父さん世代の方の「久しぶりに運動しよう」や
学生の部活動でのハードな練習で
起こりやすい怪我が肉離れです。
肉離れとは損傷部に直接的な外力は加わらず、
過剰な負荷がかかったり、過度に伸長されたり、同一の緊張状態を長時間強いられるような
場合に損傷を生じるものを言います。
原因としては、筋疲労。再発。柔軟性、コンディショニングの低下。
不適切なウォーミングアップ。などがあげられます。

太ももやふくらはぎに起こることがおおいです。
重症度によってのさまざまな、腫れ、皮下出血、硬結、関節の可動域の制限。
などがみられます。
応急処置として、安静、アイシング、圧迫、挙上。それらの処置は
筋肉の出血や腫れの軽減に効果的です。
また、当院の治療として電気療法、温熱療法、テーピング、キネシオテープ、スパイラルテープ、
ストレッチ。また、硬結と呼ばれる固まってしまい筋肉をほぐし、再発の予防をします。
肉離れになってしっまた時は早めの治療が肝心です。
しっかりと準備運動をして怪我に気を付けて運動しましょう(^^)/
2019年06月12日
こんにちは中田です。
最近、足首の捻挫の患者さんが増えてきてます。
足首の捻挫と聞くと「一週間くらいで治るでしょ?」という方が
多くいらっしゃいますが、
ハッキリ言います、、
あまいですっ!!
捻挫とは「関節が生理的可動許容範囲を超えた動きをし、
関節周囲の軟部組織(靭帯、腱など)を損傷することです。」
この軟部組織の損傷で三つに分けます。
・1度損傷⇒靭帯が伸びる
・2度損傷⇒靭帯の一部が切れる
・3度損傷⇒靭帯が完全に切れる
この靭帯というのは血管の量が少なく、
血液が行きにくいため筋肉よりも治りが悪いんです。
・1度損傷は約1週間
・2度損傷は約2~3週間
・3度損傷は約2ヵ月
当院では電気、アイシング、手技、テーピングまたは固定材料、
包帯固定の処置していきます。
特にテーピングはグルグルのガチガチに巻くのではなく、足首の可動域を残しながら、
痛みの出ない必要最低限の範囲で巻く事で日常生活に支障のでないようにしていきます。

2019年06月04日
こんにちは!今回は6月に入り梅雨の時期になると
現れやすい不調についてその予防と治療を伝えていきます!
梅雨の時期に体調が悪くなる理由の一つに
気圧の変化が関係していると言われています!
天候の変化による気圧の変動が体調に影響してきます。
気圧が低いと人間の身体は普段よりも酸素が少ない状態となり
疲労感やストレスが蓄積され頭痛になりやすいです。
また、身体の水分調節がうまくできなくなるので、むくみが顕著に
現れるのも梅雨の時期に多いです。
・予防と治療
入浴 38度~40度のぬるま湯にゆっくり浸かる。
食事 身体の水分調節をしてくれる働きのある食物
・黒豆やハト麦などの豆類
・きゅうり、ゴーヤなどの瓜類
・昆布やワカメなどの海藻類
治療 【ムクミン】
当院のおすすめ特殊治療で
足全体の筋肉をほぐし、血行を良くすることで
代謝が上がり、むくみにくい足にしていきます!
【頭痛治療】
病院で検査を受けても何も異常が見つからない場合の頭痛
筋緊張性頭痛に対しての頭痛治療を行っています。
梅雨の時期に不調がみられる場合はご相談ください。
2019年05月28日
こんにちは川合です!!
今回は、少し早いですが熱中症とその予防についてです。
まず、熱中症とは体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり
体温の調節機能が正常に働かなくなったりすることを言います。
そして、1度~3度に分類されます。
1度 立ちくらみ、筋肉の硬直、大量の発汗。
2度 頭痛、嘔吐、倦怠感。
3度(熱射病) 意識障害、けいれん、高体温(体に触れると熱い)

2度以上の場合はすぐに病院で診察をうける必要があります。
熱中症を起こした人の身体では、水分とともにナトリウムなどの電解質が失われることが多いです。
(この時期、夜中に足が攣るなどもおなじです。)
そのため、水分に加えて電解質が必要となります。
今一番いいとされているのは、塩分と水分が適切に配合された
「経口補水液」だと言われています。
予防や治療として1リットルの水に1~2グラムの食塩と大さじ2~4杯の砂糖を加えて飲むと
効率よく水分を吸収できます。
また、市販のスポーツドリンクやみそ汁、梅昆布茶などはミネラルが豊富に含まれているため
熱中症の予防に効果的です!!
当院では、足が攣る(こむら返り)や冷房で足が冷えて血行が悪い
などの症状に対して治療を行います!
患者さんひとりひとりのポイントをしっかりとみつけ筋肉をほぐし、
攣りずらい足にしたり、足全体(下半身の始まりである臀部から足の裏まで)をほぐし
血行を良くし冷えに負けない足にしていきます!!
お気軽にご相談ください。
2019年05月23日
こんにちは川合です!
今回は首、肩が凝って仕方ない!!
首、肩の動きが悪く、可動域を広げたい!!
などの方におすすめな治療の紹介です(*^_^*)
普段、お仕事で同じ姿勢が多くて首や肩を動かさず
凝ってしまう。
筋肉が張って、動かしずらくて
その分目を動かしてしまい、目が疲れる。
単に凝ってる、張ってるだけでなく
試合や大会、イベントの参加に向けての身体の改善、パフォーマンスアップしたいなどでお悩みの方に
かなり効果的な治療です!
つまり、とても多くの人に効果が得られて、スッキリします。
①まず、肩・首・背中の大きい筋肉、細かい筋肉、深くにある筋肉を分けて
ご自身の痛みやダルさ、動かしずらさの原因となるポイントをしっかりとほぐします。
②次に肩甲骨自体を動かして肩回りの動きを良くします。
肩甲骨の動きが良くなる事で、肩甲骨が引きやすくなり、また腕が挙げやすくなります。
③最後に首または背中の矯正(カイロプラクティック)をします。
首、背中の矯正をすることによって、筋肉を緩めるだけよりも、可動域が広がる。
また関節の調整をすることになるので、治療効果が持続します!!
ぜひこの治療を受けてみませんか?
ツライ身体を改善させましょう!!
2019年05月20日
こんにちは中田です!(^^)!
今日は頭痛の治療についての内容です。
私が頭痛の患者さんがいらっしゃた時にまず
「どんな痛みですか?」ときくのですが、
ズキズキやジーン、ガーンと痛い、目の奥が痛い、
この辺が痛い、頭が重い、スッキリしない、、
だいたいの方が当てはまると思います。
しかしこの患者さんの訴えの違いで治療の仕方が大きく変わります。
例えば
ズキズキ痛む方は血管の拡張が原因なので
血管の拡張が収まるような治療。
目の奥が痛い方は眼精疲労と首が原因なので
そこに対しての治療。
頭が重いのであれば気圧の変化などによる
血流不足が考えられるので、首、肩、背中周りの
筋肉をほぐし、血流を促します。
この様に頭痛とは患者さん1人1人で症状と治療の仕方が
かなり違ってきます。
頭痛の治療は患者さんのお話をしっかりと聴くところから
始まります。
病院で原因がわからない、薬を飲んでも収まらない
という方はぜひ一度当院にご相談下さい。
頭痛治療3000円
2019年05月14日
腱鞘炎とは、手首に繰り返し掛かる負担の積み重ねにより起こる症状です
特に20代、50代の女性に多い手の腱鞘炎を「ドゥケルバン腱鞘炎」と呼ばれます。
例として
:手が動きづらい
:痛みは感じ無いが手首が腫れる
:手首を使う作業やパソコン仕事をすると手首がだるく感じる
:指などを動かすと関節に違和感を感じる
などがの症状が先に出てきます
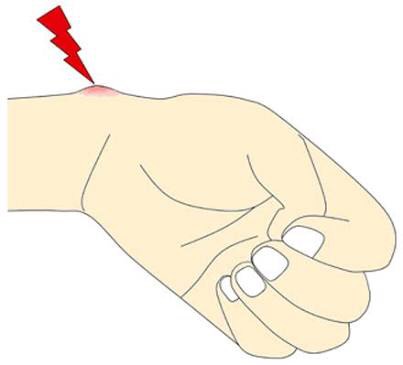
さらに症状が重くなると
1.物を持つと痛む
2.手に力が入りにくい
3.動かすと痛い
4.雑巾が絞れない
などの症状が出てきます。
〜主な原因〜
・育児
・デスクワーク
・家事全般
・最近ではスマホを使う子供達まで!!
☆治療☆
前腕の筋肉からほぐしていきます!
痛みの強い急性期の場合はアイシング、
落ち着いてきた慢性期には温めて行く事が大切です。
判断が難しい場合は、当院にご相談下さい。
2019年05月07日
今回は膝の痛みについて紹介します。
膝の痛みと言ってもいろいろあります。
膝蓋骨(膝の骨)が痛い、膝の内側が痛い、膝の外側が痛い。
今回は膝の内側に出る痛みについてです。
膝の内側に出る多くの痛みは、ぶつけた。捻った。などの原因が思い当たらない場合は
変形性膝関節症が予測されます。
変形性膝関節症とは、軟骨の変性、摩耗による荒廃、軟骨・骨の新生と増殖によって
特徴づけられる慢性、進行性の変形性関節症です。

30代後半~60代の女性に多く見られます。
症状としては、初期には炎症症状→痛み、腫れ、熱感、発赤がみられることもあります。
また初動作痛、階段の昇降(特に降りるとき)
寒冷または湿潤な時期に症状が悪化。
このような症状があてはまる場合はすぐに治療しましょう。
当院では、低周波の電気治療をして痛みの緩和をさせ
状態を確認して、温罨法、冷罨法します。
それから、痛みによる歩行で負担のかかる筋肉をほぐし
症状を悪化させないため、膝周りの筋肉のトレーニングや使い方をお伝えしていきます。
2019年04月26日
こんにちは中田です!(^^)!
「ボーンチャンネル」の動画を更新しました!
今回のテーマは「頭痛」です。
頭痛は大まかに「筋緊張性頭痛」と「病的頭痛」に
分けられます。
その違いと処置の仕方を簡単にまとめました。
2019年04月23日
こんにちは。今回は膝の痛みについてお伝えしていきます。
膝の中でも異なる3つの傷病についてです。
①鵞足炎
②腸脛靭帯炎
③ジャンパー膝

鵞足とは
膝の下の内側、脛骨(すねの骨)の上部に
3つの筋肉が付着している部分であり膝の内側の補強をしています。
この鵞足の部分に炎症が起こることを鵞足炎といいます。
陸上競技者やサッカー選手に多く
膝の内側の靭帯との摩擦やオーバーユースによる筋の緊張によって痛みが誘発されます。
急な長距離のランニング、ウォーミングアップ不足、坂道や、アスファルトでのトレーニング
などが原因にあげられます。
腸脛靭帯とは骨盤の骨から膝の下まであり、主に太ももの外側を補強している靭帯です。
ここに炎症が起きると腸脛靭帯炎になります。
腸脛靭帯炎は、オーバーユースにより腸脛靭帯と太ももの骨の下部との摩擦で炎症が起こります。
ランニングや膝の屈伸が多く繰り返される動作によって発症します。
ジャンパー膝とはその名の通りジャンプの頻回に繰り返すスポーツ選手に多く見られる
スポーツ障害であり、膝の下部に痛みを生じる。
急な加速や減速、ジャンプ、着地などの繰り返し動作により
膝に過度な張力が加わり発生する。
バレーボール、バスケットボールなどの跳躍を多用する種目で多くみられます。
その他、歩いていて膝がカクっとなる。
膝の中が痛い。不安定に感じる。何かすることに対して膝がこわい。
なんとなく膝が痛いなど。
治療は、それぞれメインになる筋肉が違うので
症状に応じた筋肉をほぐし、温熱療法、アイシング、ストレッチを
していき、スポーツの際の注意事項や日常生活の動作などの説明をします。
どれも早めからの治療が重要です。
当院にお越しください!!
« Older Entries
Newer Entries »